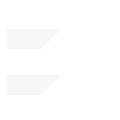1235年(鎌倉時代)、博多湾から、博多の商人、満田弥三右衛門(みつだやざえもん)と臨済宗の僧である円爾(のちの聖一国師)は宋へと旅立ちます。6年の間、二人はそれぞれ修行を積み、1241年再び、博多湾へ戻ります。聖一国師は、褝を極め、弥三右衛門は、五科を習得しての帰国でした。弥三右衛門の五科とは、朱焼・箔焼・素麺・麝香丸・織物のことで、当時の最先端技術です。弥三右衛門は、これらの技術を多くの人々に伝えましたが、織物の技術だけは、家伝の秘宝としました。これが博多織の起源とされています。

満田弥三右衛門は、博多織の独自の織紋様をつくろうと色々思索していましたが、なかなか良いアイデアが浮かびませんでした。そこで、宋の国へ一緒に行った承天寺の聖一国師のところへ相談にいきました。聖一国師は、傍らに置いてあった独鈷と華皿を持ち出して、これを使って紋様をつくることをすすめました。
独鈷とは、仏具で硬いダイヤモンドをも打ち砕く武器でもあります。そのため煩悩を打ち砕き、悟りの道を決心する象徴とされています。この紋様は、独鈷を砂の上でコロコロと回転させた回転紋様となっており、その軌跡を紋様としています。回転することで、輪廻転生や巡り廻る宇宙の構造を表す祈りの紋様とも言われています。加えて、親子縞と孝行縞という親子がお互いを思う尊い心も織り込まれており「独鈷と華皿紋様」と呼ばれていました。

関ヶ原の戦い(1600年・安土桃山時代)に徳川家康の元で手柄を立てた、黒田長政は、筑前の国五十二万石を家康から授かり、筑前黒田藩の初代藩主となりました。徳川幕府への忠誠の印として、博多に古くから伝わる独鈷に華皿柄の博多織を献上品に選びました。それ以来、毎年3月に、帯十筋と反物三定の博多織を献上することになり、「献上博多」の名称が誕生しました。献上博多織は青・赤・紺・黄・紫の5色を揃え、五色献上や虹献上と呼ばれました。刈安染の青は「仁」を、茜染の赤は「礼」を、藍染の紺は「智」を、鬱金染ないし楊梅皮染の黄は「信」を、そして紫根染の紫は「徳」を表します。江戸時代になると、キュッと締まり刀のさやの収まりが良い博多帯が武士の間で愛用されるようになりました。その後、初代市川團十郎が「助六由縁江戸桜」の」演目で、博多の着物と帯を着たことから江戸で博多織のブームが巻き起こります。現在でも歌舞伎の演目で博多帯は定番衣装として用いられています。

日本の着物の構造は、丹田の上あたりで襦袢や長着、帯を二重に巻いてお腹を冷やさないようにし、袖口からは風が入り温度調節の働きをするようにできています。呉服という言葉の原型は、古代中国の呉の国から伝わった織物のことをいうそうです。世界からの贈り物が収蔵された正倉院宝物の意匠から生まれた着物の紋様は、千有余年の時を経て現代に伝わっています。まさに着物とは、平和を祈願し、国境を超えた「平和服」ということができます。
中でもOKANOのルーツである博多織に代表される献上柄は、まさに祈りの紋様です。祈りを繋ぐ、日々の暮らしの積み重ねが智慧であり、日本の文化そのものであると考えます。